こんにちは!
この春から未経験でIT業界で働くことになった新人エンジニアです!
現在受けている新入社員向けIT研修の様子を「新人エンジニア成長記」として発信中!
今回はその第2回。「Javaプログラミング研修」が始まり、日々奮闘する様子をお届けします。
未経験からエンジニアを目指す方のヒントになれば嬉しいです。
Javaとの出会いと最初のつまずき
前回で「ICT基礎」の学習が終了、新たに「Javaプログラミング」の研修がスタートしました。
JavaはWebアプリケーションや業務システムの開発など、幅広く使われているプログラミング言語です。
とはいえ、私にとっては初めて触れる世界。最初に学んだ「変数」や「データ型」も、聞き慣れない用語ばかりで戸惑いました。
変数は“データを入れておく箱”、データ型は“その箱に入れられる中身の種類”というイメージですが、最初はピンとこず、手も止まりがちでした。
そんな中でも、講師の方や情報系出身の同期に支えられ、少しずつ理解できるように。
「自分には向いていないかも」と思いそうになることもありましたが、まずは“わからないままにしないこと”を意識して取り組みました。

条件分岐・反復処理との格闘
基本文法をひと通り学んだ後は、いよいよ実際の処理の書き方に挑戦。「条件分岐」と「反復処理」が次のテーマでした。
条件分岐は「もし○○なら〜する」といった判断処理、反復処理は「○○の間は繰り返す」といった繰り返し処理です。
概念はなんとなく理解できても、コードに落とし込むとなると話は別。
どう書けば正しく動くのか、どこで何を区切ればいいのか…とにかく試行錯誤の連続でした。
そのたびにメモを取り、疑問点は講師や同期にすぐ質問。時間があれば休み時間にも復習するなど、自分なりに工夫して学習を進めました。
未経験でスタートした自分にとって、周りに追いつくには努力が必要。
だからこそ、一つずつ丁寧に理解していく姿勢が大切だと実感しました。

焦りを手放し、自分のペースで進む
研修が進むにつれて、「メソッド」「引数」「戻り値」「配列」など学ぶ範囲もどんどん広がっていきました。
その中で、理解が追いつかず焦ることも。ひとつ質問をしている間に、次のトピックに進んでしまうような感覚に不安を覚えました。
そんなとき、講師が「着実に知識はついてるし、コードを書くスピードも上がってるよ」と声をかけてくれました。
その言葉で、自分は“理解できないこと”よりも“周りと比べて遅れていること”に焦っていたのだと気づきました。
劣等感に近い感情を抱いていたのかもしれません。
でも、本来の目的は“周りより早くできること”ではなく、“現場で通用する力を身につけること”。
そう思い直してからは、焦りよりも前向きな気持ちで学習に向き合えるようになりました。

今回は少しまじめな話になってしまいましたが次回は「少人数で実際のシステム開発」に取り組んだ内容をお届けします!
目的を認識した私の行動、メンバーとの協力、そしてその結果は…。
そんな私の奮闘記を、ぜひ次回も読んでいただけたら嬉しいです!
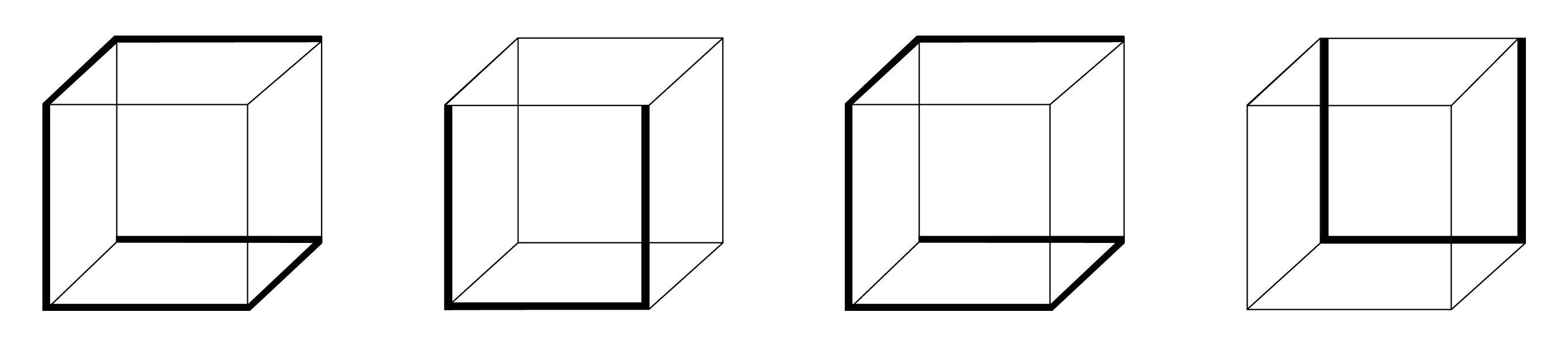



コメント