この春から未経験でIT業界で働くことになった新人エンジニアです!
現在受講している新入社員向けIT研修の様子を「新人エンジニア成長記」として発信中!
今回はその第4回として、Javaプログラミング研修での初テスト、その後のレベルアップした学習内容について、感じたことや学んだことをお届けします。
Java研修 初テストの振り返りと課題の発見
テストの概要
Javaの開発演習を一通り終えた後、初めての理解度テストに臨みました。
Java研修のテストは、以下の3パートで構成されていました。
- 知識問題:Javaの文法や構造に関する選択問題
- リーディング問題:提示されたコードの挙動を読み取り、出力結果を答える問題
- ライティング問題:仕様に従ってコードを自ら記述する問題
範囲としては、入門レベルの内容で「変数とデータ型」「条件分岐・ループ処理」「メソッド」「配列」など、基本的な構文理解が問われました。
実際に解いてみて:結果と学び
知識問題(正答率:80%)
Javaの基礎知識に関する問題では8割正答。
誤答の原因は以下の通りです:
char型の値はシングルクォーテーション(’)で囲む必要があることを失念- 整数型の配列は初期値として0が代入されているという仕様を見落とし
基礎とはいえ、細かい仕様まで正確に理解することの重要性を実感しました。曖昧な知識は実務レベルでは致命的になり得るので、ここは今後の学習でしっかり補強していきます。
リーディング問題(正答率:100%)
提示されたコードの動作を読み解く問題は全問正解でした。
理由は、1行ずつ処理を追い、変数の状態変化を紙に書き出して確認したことです。こうすることで、コードの中で「いつ」「どこで」「何が」変化するかを視覚的に把握できました。
この手法は、実務におけるデバッグ時に変数の状態が意図通りに変化しているかを追跡することが可能になり非常に役立ちます。
今回のようにコードを静的に1ステップずつ見える化する習慣があれば、バグの早期発見につながると感じました。
ライティング問題(正答率:33%)
ここが一番の課題でした。3問中1問のみ正解。
問題を解いていて感じたのは、「理解」と「書ける」は別物ということです。
とくに「メソッド」や「配列」の知識は持っていても、実際に設計し、コードとして表現する段階になると急に手が止まりました。
応用力と設計力が足りていないという、今の自分の限界を明確に認識できました。
テストを通して得た気づき
今回の経験を通じて強く感じたのは、インプットとアウトプットのバランスの重要性です。
教材を読んで理解したつもりでも、「実際に書いて動かす」段階では、思考が止まりがちになる。
これは「知っている」と「使える」の違いであり、今後の学習では以下を意識していきます。
- コードを読むだけでなく、実際に手を動かす量を増やす
- エラーや詰まった部分は、「なぜできなかったのか」を明文化する
- 書けるようになるまで、似た課題を何度も繰り返す
Java基礎編の学習に突入:核となる概念との対峙
次の学習内容の概要
開発演習の初期フェーズを終え、いよいよJavaプログラミング基礎編に入りました。
ここからは、Javaを単に「書ける」だけでなく、「設計できる」状態に近づけるための概念理解が求められます。
具体的には以下のようなテーマが中心です:
- クラスとオブジェクト
- オーバーロード
- ポリモーフィズム(多態性)
- 例外処理
このあたりはJavaの「核」ともいえる部分であり、研修チーフからも「ここが理解できるかどうかが今後を左右する」と念押しされ、自然と身が引き締まりました。
学習中の悩みと乗り越えた壁
学習が始まってまず直面したのは、「フィールド」「インスタンス」「コンストラクタ」などの知らない単語の連続でした。
まるで異国語のようで、理解の取っかかりすら見えない感覚。
周囲は専門学校や情報系大学を出た経験者ばかり。自分は未経験からの挑戦。
正直「初歩的な質問をしても大丈夫なのか」と不安になり、質問を飲み込んだ瞬間もありました。
しかし、未経験でITエンジニアを目指しており、質問することは恥ずかしいことじゃないと考えました。
以前の記事でも書きましたが、この研修を受けている目的は「現場で通用する力を身につけること」。
そこで、勇気を出してわからないことは積極的に質問するようにしました。
すると、驚いたことに多くの人が快く答えてくれました。
「聞かれる側にとっても、丁寧に聞いてくれると嬉しいものなんだ」と気づきました。
それからは、自分がただ質問するだけでなく、相手が答えやすくなるような聞き方も意識するように。
例えば:
- まず自分で調べてみた内容を伝える
- 質問を具体的にする(「なぜ動かないか」ではなく「〇〇を使うとエラーになる理由は?」)
この経験を通して、言葉の意味を一つずつ理解できるようになっただけでなく、チームの中でどう協力して学び合うかという姿勢も身につきました。
一人ではなく、仲間と共に学ぶということ
今回の研修で学んだのは、プログラミングスキルだけではありません。
- わからないことを素直に伝える勇気
- 相手の立場に立って質問する姿勢
- 周囲と協力して課題に取り組む力
これらは、今後エンジニアとして一人で仕事を回すのではなく、チームで成果を出すために欠かせない力です。
「仕事は一人じゃできない」——この言葉を、今回ほど実感したことはありませんでした。
今回のまとめと次回予告
今回は、Javaプログラミングにおける初テストの振り返り、そしてその後のステップアップした学習内容と気づきについてお伝えしました。
特に強く感じたのは、
「理解できる」と「書ける」はまったくの別物だということ。テキストを読んで満足するだけでは、実務レベルでは戦えない。
実際に手を動かし、試行錯誤しながらコードを書くことが、真の理解につながる——この経験からそう確信しました。
また、改めて実感したのが「仕事は一人ではできない」ということ。
これまでも頭では分かっていたつもりでしたが、実際に仲間と協力しながら学び合ったこの体験が、自分の中に深く刻まれました。
次回は:
- Java 2、3回目の理解度テスト
- 2回目のチーム開発演習
をお届け予定です。
次回もぜひお読みいただけると嬉しいです!
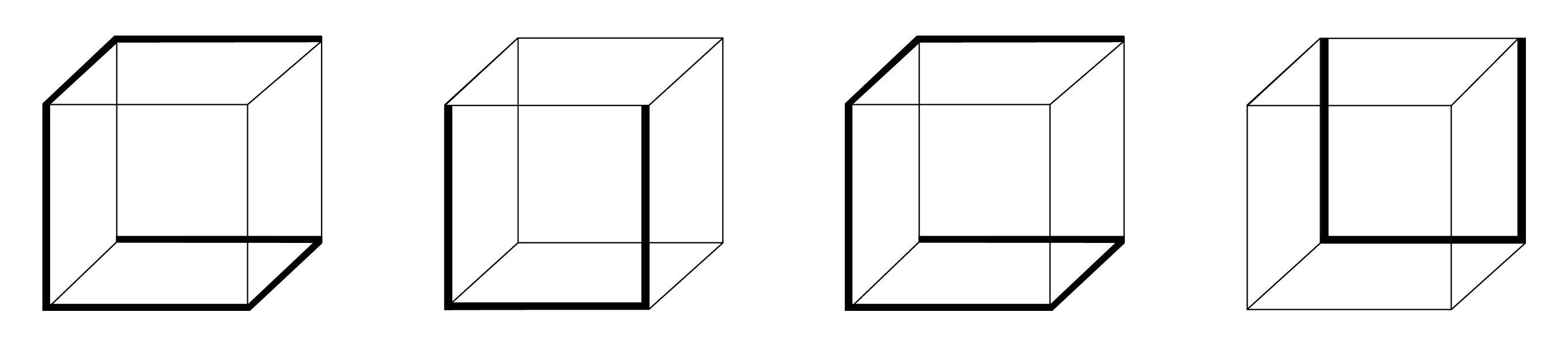



コメント